ロシア ウクライナ 松里公孝 學士会報
二〇二二年二月二十四日早朝、ウラジミル・プーチ
ン大統領の事実上の宣戦布告の約十五分後、ロシア軍
が発射した百発以上のミサイルがウクライナの軍事施
設を破損した。 続いて、北(主にベラルーシとジト
ムィル州間の国境)と南(クリミア)から陸上部隊が
侵入した。
その後、本稿執筆 (二〇二五年一月)までの戦争の展開は四期に分けることができる。 ①開戦からイスタンブル停戦交渉まで。
②その後、ロシア軍のハルキウ州・ヘルソン州からの撤退(二〇二二年十一月九日)
まで。
③その後、ウクライナ軍反転攻勢の失敗 (二〇
二三年十一月)まで。
以上の結果として、二〇二三年秋頃から、ウクライ
ナ国内の徴兵忌避が顕著になり、徴兵も路上での人狩
りのような様相を呈するようになった。開戦前から、
ウクライナのエリート(国防大臣、キエフ市長、前大
統領、軍のスポークスウーマン等々)の子供は欧米で
高等教育を受けている。ロシアが侵略してきたからと
いって、親は自分の子供に「国の危急の時だから帰国
して入隊しなさい」とは言わない。それどころか、テ
レビで「うちの子は軍隊生活に耐えるようにはしつけ
ていないから」などと開き直る。ポロシェンコ前大統
領の息子は、二度令状を受け取りながら徴兵事務所に
現れないので、とうとう指名手配されてしまった。ウ
クライナは民主的なので、こうした話はソーシャルメ
ディアだけでなく国が管理するテレビでも公然と拡散
する。国民はばかばかしくなって、ますます徴兵忌避
するようになる。
④期に入ると、戦争の主舞台は南部から再びドンバ
スに移ってきた。二〇二四年二月にはアヴデエフカ、
十月にはウグレダルとセリドヴォ、二〇二五年一月に
はクラホヴォをロシア軍が占領した。二〇二四年初
頭、プーチンがドンバス戦線に本腰を入れ始めたと
き、私は、彼が戦争終結を視野に入れ始めたのではな
いかと思った。ロシアの公式の戦争目的は、ドンバス
住民の保護である。大統領にロシア軍の国外展開を許
した上院の決議には、「NATO拡大の阻止」、「クリ
ミアへの陸上回廊の形成」などは書かれていないし
かし、プーチン政権の優先目的はこの二つであり、だ
からロシア軍は開戦後の二年間、バフムトを除けば、
ウクライナがドンバスに作り上げた防衛線=諸要塞都
市の清算に主力を投入することはなかったのである。
ロシア軍がドンバスに主力を移してからも、諸要塞
都市は簡単には攻略されなかった。ドネツク市につい
ては、戦線は二十キロメートル以上離れてくれたが、
二〇一四年のドンバス紛争の開始以来、最も多くの被
弾犠牲者を出してきたゴルロフカ市のすぐ隣では、 ま
だウクライナがトレック市に陣取っている。兵員も兵
器も足りないもとでドンバス最前線に踏みとどまって
いるウクライナ軍の精神力には驚くが、これには負の
側面がある。
通常、戦争の布陣においては、最前線が突破される
ことは想定して、第二戦線を強化するものである。日
露戦争のとき日本は奉天で勝ったが、ロシア軍の主力
があったのはザバイカル州(こんにちのブリヤチヤ)
であった。ソ連は、第三次世界大戦が起こった際は、
最前線である東欧やバルト共和国は突破されるのを想
定し、ウクライナ、ベラルーシ、沿ドニエストルでN
ATO軍を食い止めるつもりであった。ところが現ウ
クライナ政府は、おそらくドネツク州西端ポクロフ
スク市を中心点にして作るべきだった第二戦線の建設
を怠り、そのかわりロシア軍に力攻めで追い出される
まで最前線都市にとどまり続ける。撤退命令が出ず、
各部隊が自己判断で三々五々撤退するものだから、損
失も大きくなる。 この傾向は、緒戦における国軍とア
ゾフ軍のマリウポリ立籠りにはや現れていた。戦争初
期に九千人から一万五千人の兵力を失ってしまったの
である。
露ウ両政府に奇妙に共通しているのは、通常は停戦
後の和平交渉で議論される問題を停戦段階で解決しよ
うとしていることである。ウクライナの保障問題につ
いては前述した。 プーチン政権も、まず現境界線で停
戦し、ウクライナの中立化や占領四州の帰属について
は和平交渉で話し合うという普通の手続きを拒否して
いる。「我々は一度ミンスク合意(二〇一四、一五年)
で騙された。停戦はウクライナ軍強化のための時間稼
ぎとして使われた。だから今回は、四州のロシア帰属
をウクライナと国際社会が認め、ウクライナNATO
非加盟をいま約束しない限り停戦はしない」とプーチ
ンは言う。トランプ新政権が、「占領を公式には認め
ないが、実効支配としては我慢するから、今の境界線
で戦争をやめてくれ」と暗に頼んでいるときに、プー
チンの姿勢は強硬に過ぎると言わねばならない。
の赤軍のドニプロ渡河が成功例である。「一九四三年の十月
革命記念日にクィウで式典を行うためにスターリンが急がせ
た」というのはソ連の大衆映画が広めた俗説で、本来渡河 作
戦とは、強引急速に大部隊を渡河させないと先遣隊が殲滅さ
れてしまう作戦なのである。

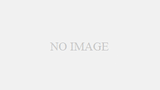
コメント