朝4時から報道陣の列が…世界が注目した中国の最高権力機関「全人代」 李強首相の演説から見えた中国政府が抱く危機感とは?© TBS NEWS DIG_Microsoft
中国で最高権力機関と位置付けられている全人代=全国人民代表大会。今年は3月5日からおよそ1週間にわたって開かれた。世界中の報道陣の注目を集める全人代で中国政府が強調したのは“消費低迷への危機感”だった。
朝4時から並ぶ報道陣 開門後は猛ダッシュ 会場に一番乗りしたいワケとは?
全人代の開幕式が行われる日、報道陣の朝は早い。今年、開幕式が行われたのは3月5日、午前2時半に起床し4時すぎに会場となる人民大会堂の周辺に到着した。会場に通じるゲートはまだ開いていないもののすでに複数の海外メディアが並んでいた。5時を過ぎると列もだいぶ長くなり周囲の緊張感も高まって来る。
午前6時すぎ、ゲートが開くと並んでいた記者たちが一斉に走り始めた。機材を持ったカメラマンも全力でダッシュしている。会社に入社してから11年になるが、全力で走ったのはこのときがはじめてだった。会場入り口の荷物検査で待たされるなどハプニングはあったものの、10位前後で報道席に入ることができた。
なぜ、海外メディアが競って会場に一番乗りしようとするのか?
それは海外メディアにとって全人代が中国の最高指導部を直接撮影することのできるほぼ唯一の機会だからである。特に習近平国家主席を直接見ることのできる機会は全人代を除くとほぼ皆無である。普段は中国の国営メディアが配信する編集された映像を通してでしか習近平国家主席を見ることはできない。だからこそ、少しでも良い場所から撮影しようと場所取り競争が生まれるのである。
習近平国家主席にはなぜかお茶が2つ…カメラが捉えた中国の最高指導部の姿とは?
朝4時すぎから並んでいたこともあり、今年は良い撮影スポットをおさえることができた。開幕式が行われる午前9時が迫るとスタッフが慌ただしく準備をはじめる。幹部が座る舞台の上では一直線に並んだ女性スタッフが一糸乱れぬ動作でお茶をいれていく。
習近平国家主席が座る席にはなぜかカップが2つ置かれている。他の幹部との権威の違いをあらわしているのか、その理由は定かではない。
午前9時、開幕式がはじまると習近平国家主席を先頭にナンバー2の李強首相ら最高指導部が入場する。
今回、李強首相は1時間ほどかけて「政府活動報告」を読み上げたが、その間、習近平国家主席が固い表情を崩すことはなかった。しかし、李強首相が「活動報告」を読み終え自分の席に戻ったタイミングで習近平国家主席が声をかけ一瞬笑顔を見せたのである。その後も、2人がたびたび言葉を交わす場面が見られた。こうしたところから、中国を率いるトップとナンバー2の関係性をわずかながらうかがい知ることができる。
全国から約3000人の代表が集結 全人代で首相が読み上げた「政府活動報告」の中身とは?
中国で最高権力機関に位置づけられる全人代には全国の省や軍、少数民族の代表ら約3000人が出席する。各地方に置かれている人民代表大会の選挙によって代表が選ばれていて、日本の国会のように国民の直接選挙で選ばれているわけではない。
開幕日には首相が去年の政府の実績と今年の方針をまとめた「政府活動報告」を読み上げる。その年の政府の予算案や司法機関である最高人民法院、最高人民検察院の活動報告も公表される。最終日には代表による採決も行われるが、否決されることはまずない。
海外メディアの関心が高いのは「政府活動報告」だ。
今年注目を集めたのは中国に対して強硬な姿勢をとるアメリカのトランプ政権への言及である。
李強首相 「一国主義と保護主義が激化し世界経済の循環を阻害している」
李強首相はアメリカを名指しすることはしなかったものの、トランプ政権を念頭に、国際環境が厳しさを増し中国の貿易や科学技術に影響を与える可能性があるという認識を示した。
さらに国内の経済状況についても厳しい見通しを示した。
李強首相 「国内においては経済の持ち直しの基盤がまだ盤石ではなく需要が不足している」
李強首相は「とりわけ消費が落ち込んでいる」と強調。「消費を押し上げるための特別行動を実施する」と宣言した。
超長期特別国債1兆3000億元(日本円で約26兆8000億円)を発行し、消費財の買い替え支援に3000億元(日本円で約6兆2000億円)、設備更新の支援に2000億元(日本円で約4兆1000億円)あてるという。
1年間で約300万店の飲食店が倒産 中国政府も危機感を抱く消費低迷の現場を取材
政府も危機感を抱く消費の低迷。
大きな影響を受けているのが飲食店だ。中国のコンサルティング会社「紅餐」によると、2024年に中国で倒産した飲食店はおよそ300万店にのぼり過去最多を記録したという。
実際、北京市中心部のショッピングモールのなかには多くの飲食店が潰れ、店がそのまま放置されている場所もある。北京市内で話を聞いてみると「外食を減らしている」と答える人が多かった。
北京市民 「景気が良くないので支出を減らそうと思っています」
北京市民 「外食に使うお金は以前と比べて少し減っています。最近はお金を稼ぐのが大変だし貯金しようと思っています」
2月下旬、取材班は北京市郊外の串焼き料理店に向かった。この店は2023年の夏にオープンしたものの客足がふるわず、去年の12月に閉店したという。
この日、店に来ていたのは飲食店を専門に扱うリサイクル業者。倒産した店から厨房の機器を安く買い取り、別の店に販売している。厨房に置かれた冷凍庫やシンクなどを次々と運び出してトラックに積み込んでいく。この日回収された機器は4000元(日本円で約8万円)で買い取られた。
料理店のオーナー 「ビジネスの状況はずっと良くありませんでした。店をオープンするための費用や家賃、人件費なども合わせて2年で200万元(日本円で約4000万円)弱を失いました。いまは不景気なので商売が難しいです」
「重要なのはコスパ」 飲食店“大量倒産”の背景とは?
なぜ1年間で300万店もの店が潰れたのか?
私たちは、6年間にわたって飲食店を相手にリサイクル業を営んできた男性にインタビューすることができた。
飲食店専門のリサイクル業を経営する 安大為さん 「消費が落ち込んでいて価格が高い店に対するニーズは明らかに減少しています」
安さんによると、景気の先行きの不透明感が強まっていることもありビジネス会食の機会が以前より少なくなっていることや、市民の給与所得が減っているため、比較的価格の高い高級店が苦戦しているのだという。
さらに、新型コロナの影響でリストラされた人たちが外食産業に流れ込み、2023年の上半期だけで200万店近くの飲食店がオープン。供給過剰になっていたことも飲食店の大量倒産につながった要因だという。
最後に、今後、飲食店が生き残るための条件についても聞いてみた。
飲食店専門のリサイクル業を経営する 安大為さん 「100元(日本円で約2000円)以内に客単価を抑えて利益を出せる店が生き残っています。一番重要なのはコスパです」
コスパが重視される中国。縮小していく消費にどのように対応していくのかが経済を立て直すためのカギとなりそうだ。
取材後記
全人代で消費の落ち込みに対する強い危機感を示した政府は、具体的な消費振興策として消費財の買い替え支援策を打ち出した。こうした政策は去年から行われていて、スマートフォンや自動車、家電などを買い替える際に補助金が出る。今後は支援する対象をさらに増やすという。
しかし、こうした中国政府の政策について「需要を先食いしているだけ」(中国経済の専門家)という指摘もある。消費を増やすためには賃上げや社会保障の整備などを通して安心してお金を使うことができる環境を整える必要がある。ただ、最低賃金の引き上げや社会保障の整備は多くの企業が絡む話でもあり、一筋縄ではいかないだろう。
それでも、中国政府は補助金の支給という一時的な解決策にとどまらず、抜本的な改革に乗り出すのか。政府のかじ取りに注目していきたい。
文 JNN北京支局 松尾一志
撮影 JNN北京支局 室谷陽太


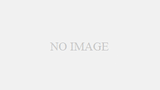
コメント