近年、長期化する「中高年ひきこもり」の存在が社会問題となっています。背景には、就職後の人間関係や健康上の理由、家庭内の出来事など、さまざまな要因が絡み合います。本記事では事例を通じて、引きこもりの長期化が家計や生活に及ぼす影響、そして共倒れを防ぐために取り得る現実的な対策について見ていきます。
引きこもり息子への「淡い期待」が打ち砕かれる
「母さん、おれ働けないよ。外に出るなんて無理だと思う」
その言葉を聞いた瞬間、「このままでは共倒れになってしまうかもしれない」という恐れと、自分の責任を問う気持ちが同時に芽生えた──そう語るのは、東京都在住の加藤真理子さん(仮名・62歳)。20年以上前に夫を亡くして以来、ひとり息子の翔太さん(仮名・35歳)と二人暮らしを続けてきました。
加藤さんは事務職として定年まで勤め、退職金とこれまでの貯蓄を合わせて老後資金は1,800万円に。さらに月12万円の年金収入もあり、「節約すれば息子と暮らしていける」と考えていました。
大学卒業後に就職した会社を人間関係のトラブルで退職して以降、息子はアルバイトを転々とし、30歳を過ぎた頃からは家にこもる生活に。再就職の話を振っても「そのうち探すよ」と言葉を濁すだけでした。
それでも、翔太さんもいつかは働き始めるだろう──そんな淡い期待を抱いていました。
しかし、加藤さんが将来の生活について真剣に話を切り出したある日。
「私も年を取るし、もし介護が必要になったら……」と口にした途端、翔太さんは視線を逸らし、「母さん、おれ働けないよ」と呟きました。
その言葉は、単なる拒絶ではなく、息子自身が抱える閉塞感や諦めの深さを突きつけるものでした。加藤さんは「このままでは息子も、そして自分も、身動きが取れなくなる」と直感したといいます。
内閣府『こども・若者の意識と生活に関する調査』(2022年)によると、40〜64歳の「中高年ひきこもり」は全国で約84万人。長期化するほど社会復帰は難しくなり、「8050問題(80代親と50代子の共倒れ)」が現実味を帯びます。加藤さん親子も、年月が経てば同様の深刻な状況に発展する可能性も否定できません。
息子に「自分で生きていく力」を身につけさせるアプローチ
家計と生活再建の両立には、以下のようなアプローチが求められます。
●小さな外出から始める
長年ひきこもり状態だった人は、いきなり就職を目指すより、通院や地域の交流会への参加など“小さな社会接点”を増やすことが重要。社会福祉士や就労支援員が同行する「ステップ型支援」もあります。
●第三者による家計管理
親の死後に備えて、成年後見制度や家族信託で生活資金や不動産の管理を第三者に委託する方法があります。金銭トラブルや生活困窮に陥るリスクを減らす効果があります。
●就労支援サービスの活用
∟地域若者サポートステーション(39歳まで)
∟生活困窮者自立支援制度(年齢制限なし)
∟就労移行支援事業所(精神・発達障害や適応障害の場合)
利用にあたっては、親ではなく支援員から提案する方が本人の受け入れがスムーズになるケースも多いといいます。
●親子間ルールの明文化
生活費の負担割合や将来の居住条件などを、口約束ではなく文書にしておくことも重要です。「親の資産は無限ではない」という現実を、具体的な数字と共に共有することで、子の行動変化につながる可能性があります。
「お金を減らさないこと以上に、息子が自分で生きていく力を持つことが大事。遅くても、今がそのスタート地点です」
加藤さんはそう語り、支援員と共に月1回の外出から息子の生活を少しずつ広げています。
引きこもり状態が長期化した場合、「働かせる」より先に「社会とつながる」ことから始める必要があります。
親の体力・資金に余裕があるうちに、第三者支援・家計管理・将来設計を同時に進めることが、共倒れを防ぐ現実的な道筋です。

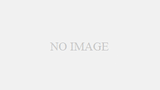
コメント