都心のタワーマンションを相続したと聞けば、「うらやましい」と思う方も多いかもしれません。しかし実際には、相続した不動産がその後の生活に重くのしかかるケースもあります。固定資産税、管理費、修繕積立金、そして将来の売却リスク――。中でも「タワマン相続」は想像以上に“荷が重い”と語る人も。本記事では、両親の住んでいたタワーマンションを相続した50代男性の後悔と、背景にある制度的課題を見ていきます。
「自慢だったんですよ、最初は」
都内で働く会社員の田村さん(仮名・54歳)は、数年前に亡くなった両親が残したタワーマンションを相続しました。
間取りは3LDK、都心の駅から徒歩5分という好立地。購入当時の価格は1億円近かったといいます。
「親が購入した当時、タワマンはまだ珍しい存在でした。知り合いに『うち、親からタワマン引き継いだんだよ』って言うと、“勝ち組”みたいな扱いをされました」
最初のうちは、その“肩書き”に満足していた田村さん。しかし、次第に現実が見えてきたといいます。
「固定資産税が年間で30万円を超えるとは思いませんでした」
加えて、毎月の管理費と修繕積立金は合計で約5万円。住宅ローンがないとはいえ、年間で90万円以上の支出が生じています。
「住んでいる分にはまだしも、将来、子どもが住まないなら“負動産”になるかもしれない」
田村さんにはすでに独立した娘がいますが、タワマンの場所は娘夫婦の生活圏とは異なるため、将来的に住む予定はないとのこと。
「いざとなれば売ればいい」と考えていた田村さん。しかし、いざ不動産会社に相談すると、思わぬ指摘を受けました。
「このマンション、今後の大規模修繕費が不足気味ですね。購入希望者から敬遠されることもありますよ」
築年数が20年を超えると、タワマンでも価格が落ち着き始めます。とくに近年は、「管理組合の財政状況」や「建物のメンテナンス履歴」が重視されるようになり、売却の難易度が上がっているといいます。
さらに悩ましいのが「相続税評価額」と「実際の売却価格」の乖離です。
相続税は、建物部分については「固定資産税評価額」、土地部分については「路線価」をもとに計算されます。しかし、高層階のプレミアム感や都心立地の希少性は、こうした評価基準では十分に反映されず、実際の市場価格よりも低く算定されるケースが少なくありませんでした。
この仕組みを利用し、高層階のタワーマンションを相続税対策として購入する、いわゆる「タワマン節税」が一時期話題となりましたが、2024年1月からは制度が見直され、階層や実勢価格を加味した補正が行われるようになっています。
ただし、市場価格に見合った税額を求める動きが強まる一方で、「現金化しにくい不動産」が相続後に手元に残るリスクは依然として残っており、評価制度の改正だけでは解決できない課題もあります。
国も注目する“空き家予備軍”としてのタワマン
田村さんは現在もタワマンに居住していますが、「体が動くうちに処分を考えたほうがいいかもしれない」と感じているそうです。
「管理組合の役員が持ち回りで回ってくるのも、60代、70代になってからだとしんどいですよね。施設の設備更新の議論も増えるし、“住む場所”というより“責任”のように感じてしまう瞬間があります」
国土交通省の報告書では、都市部の高層マンションの“空き家予備軍”化が懸念されています。とくに親世代が住んでいたタワーマンションを子世代が相続する場合、「居住ニーズのズレ」や「維持コストの重さ」から、数十年後には空き家や管理不全マンションになるリスクも指摘されています。
「タワマン=資産」というイメージは根強いですが、維持できる体力がなければ、その資産は“責任”や“負担”に変わる――田村さんのようなケースは、今後ますます増えていくかもしれません。
「子どもにこの家を継がせたいとは思いません。むしろ、身軽に生きてほしい」
そう語る田村さんの言葉には、所有から「活用・流動」へと価値観がシフトする時代の空気がにじんでいます。
「最初は良かった」と語るタワマン相続も、その先に見えたのは“自由”ではなく、“見えない制約”でした。家を持つこと、継ぐこと――その意味を、今こそ見直すタイミングなのかもしれません。

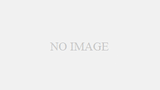
コメント