議員定数削減は逆効果?チームみらい党首・安野氏が指摘する懸念点「一番失われるのは“政治家の新陳代謝”」© ABEMA TIMES (Microsoft)
高市政権誕生の立役者になった日本維新の会だ。彼らが連立の絶対条件として突きつけたのが議員定数の削減だ。両党の合意文書には衆議院の定数1割削減を目標として、この臨時国会で法案提出し、成立を目指すと明記されている。
議員定数の削減は13年前、民主党政権時代の野田佳彦総理が、自民党・安倍晋三総裁との党首討論で約束していた。しかし抜本的な削減はされず、今なお与野党から賛否両論が出ている。そもそも定数削減は国民にとってメリットがあるのか?『ABEMA Prime』では日本維新の会の議員らと議論した。
■議員定数の削減、国民にとってのメリットは?
議員定数削減は逆効果?チームみらい党首・安野氏が指摘する懸念点「一番失われるのは“政治家の新陳代謝”」© ABEMA TIMES (Microsoft)
議員定数削減を推し進める日本維新の会幹事長代理の金村龍那衆院議員は、「2012年当時に野田総理の民主党は、45人削減の法案を提出している。『国民に痛みを求めるなら、議員みずから痛みを伴う改革をすべきだ』としたが、実際には5人しか削減されなかった。現在も当時の480人から、15人しか減っていない。政治不信にケジメをつける意味でも、維新は1割削減を掲げた」と説明する。
議員削減による、国民にとってのメリットについては、「社会保険料の引き下げなどの構造改革は、損をする人も得をする人もいる。そうした状況下で、政治家が政治不信を招いた責任を取るために、身を切る改革をすることに反対は出ないだろう。日本に必要な改革を実行する入口論だと思っている」。
一方で、チームみらい党首の安野貴博参院議員は、議員定数削減に反対の立場を取る。「『仕事をしてなさそうな議員は減らしていい』という感情論は理解できるが、1割減は失うものも大きく、冷静に見るべきだ。一番失われるのは“政治家の新陳代謝”で、二世議員じゃない人々の参入障壁が高くなる。我々のようなスタートアップ政党も生まれなくなるかもしれない」。
そして、「維新も元々、スタートアップ政党から始まり大きくなったが、最初の選挙は8割が比例で当選している。政治家の新陳代謝を大切にしないと、どんどん国民の新しい声が届かなくなってしまう懸念がある」とした。
人口あたりの国会議員数を、第1院と第2院(衆議院・参議院、上院・下院)で合計したデータがある。「日本の国会議員は多いのか。OECD諸国を見ると、人口比率で38カ国中36位(100万人あたり5.6人)と、あまり多くない。1位のアイスランド(176.5人)とは議会制度も違い比較しづらいが、規模が似ている議員内閣制の国を見ても、ドイツ(9.7人)の半分、イギリス(21.7人)の4分の1程度でしかない」。
こうした現状を踏まえた上で、「比例から削減して『身を切る』と言っても、自民や維新はあまり比例の割合が高くない。ここは冷静に見る必要がある。選挙制度改革は、私も維新と似た考え方だが、『1丁目1番地』として比例定数削減をやるのはどうなのか」と問う。
研究者の山内萌氏は「定数削減は本質的な議論ではない。仕事をしていない政治家に対する、ある種のヘイトに対して、『定数削減で身を切る』というパフォーマンスにしか見えない」といった疑問を持つ。
■“議員を減らす”精神論をどう受け止めるか
議員定数削減は逆効果?チームみらい党首・安野氏が指摘する懸念点「一番失われるのは“政治家の新陳代謝”」© ABEMA TIMES (Microsoft)
かつて国会には、衆議院選挙制度に関する調査会が設置され、2016年に答申(骨子)が出されていた。「現行の小選挙区比例代表並立制を維持」「衆議院議員の定数は多いとは言えないが、各党が削減を公約に掲げていることから、削減するなら10削減(小選挙区6/比例4)」「比例代表選挙は現行11ブロックを維持」「選挙区間の一票の較差は2倍未満」などの内容で、答申後の2016年に475議席から465議席へと削減された。
員定数削減を検討した国会の調査会メンバーだった、津田塾大学教授の萱野稔人氏は、「野田総理と安倍氏が削減を約束して、その後の安倍政権で話し合ったが、各党の利害が衝突して話がまとまらなかった。そこで利害関係のない有識者会議が素案を作ることになった」と振り返る。
有識者会議での議論については、「定数削減が本当に成立するのかと検討し、結果的に『10人削減』を答申した。日本は人口比でいうと議員数が少なく、これは『議論がスリム化される』ことより、『国民の権利が削られる』ことに近いという共通認識があった」と語る。
過去を振り返り、「1925年の普通選挙制導入時は、衆議院は定数466で、今の465より多かった。しかし当時は、まだ人口6000万人で、今の半分しかいない。歴史的に見ても、極めて少ない議員数で国会を運営しているのが現実で、『さらに削る根拠はない』と調査会でも確認した」という。
しかしながら、「ほとんどの政党が定数削減を公約に掲げたため、無視できなかった」のだそうだ。「明確な根拠はないが、無視すると調査会の正当性がなくなるため、削れるギリギリの範囲で答申した。削減を求める側が、まずは『削減によるメリット』を出す必要があり、『身を切る改革でやらないと』と言うのは精神論に聞こえる」。
定数削減のデメリットとしては、「代表者を選べる幅が少なくなる。小選挙区の定数を削ると、地元で代表者を選べなくなる。人口の少ない鳥取や島根では、大きな選挙区を作る必要が出てきて、『鳥取県民だが島根の偉い人を選ばないといけない。地元じゃないからリアリティーがわかない』となる」と解説する。
反対にメリットとしては、「時代の変化の中で、議論に欠けるコストをどの程度節約するか。新陳代謝されないと、声だけが大きい“ゾンビ政党”も残る。定数削減により、決定すべきことを決定できない議論をスリム化できる。調整のコストを考えると、スピーディーに決定できるのはメリットだ」とする。「衆参の役割分担も考えられる。参議院が反対しても、だいたいは衆議院で決まる。であれば、衆議院は小選挙区を多めに、参議院は比例を多くして、専門家が発言できるよう構成を変える、といった議論もありうる」。
日本維新の会の金村氏は「日本の改革のために、利害関係者が変わるため、痛みを伴う、これは精神論だが、やらなかったときに、政治家はどういう信頼を保つのか。国民そっちのけで政治改革をし続けたため、“失われた10年”が“失われた30年”に伸びた」と指摘する。
加えて、「議員定数を削減する上で、一番のポイントは制度設計だ。我々は選挙制度改革も提案しているが、これはセットで議論すべき。『定数削減するが、制度も社会に追いついていない』と提案しており、そこを切り分けるのは難しい」と話した。



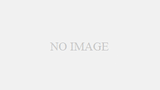
コメント