老いなき世界
著者 デビッド・A.シンクレア/著 シンクレア,D.A.
マシュー・D.ラプラント/著 ラプラント,マシュー D.
梶山あゆみ/訳 カジヤマ,アユミ
出版者 東京 東洋経済新報社
出版年 2020.9
生命の誕生プロセスについては詳しいようだ。
生命の誕生
地球と同じくらいの大きさの惑星を想像してほしい。
その惑星と恒星との距離は、地球から太陽までの距離にほぼ等しい。
自転のスピードは地球よりわずかに速く、1日はおよそ20時間である。
塩水の浅い海で覆われ、大陸と呼べるようなものは見当たらない。
黒い玄武岩の島々の連なりが、ときおり思い出したように水面から顔を出しているだけだ。
大気の組成は、私たちが吸っているものとは違う。
窒素、メタン、二酸化炭素からなる湿った有毒のガスが惑星を取り巻いている。
酸素はない。生命も存在しない。
この惑星の正体は、約4億年前の地球だ。そこは無慈悲で情け容赦のない場所である。
熱い空気が渦巻き、火山が火を噴く。稲妻が走り、混乱が支配する。
だが、それもまもなく変わろうとしている。
比較的大きな島に熱水噴出孔が点在していて、その脇に水が溜まっていった。
地表はどこもかしこも有機分子に覆われている。
これは、隕石や彗星に付着して降ってきたものだ。
乾いた火山岩の上に載っているだけなら、分子は分子のままである。
しかし、温かい水に溶けたあと、水溜まりの縁で濡れたり乾いたりを繰り返すうち、
特殊な化学反応が起きた。
核酸が生じ、その濃度が高まり、分子同士がつながっていく。
ちょうど、海辺の潮溜まりで水が蒸発すると、
塩の結晶ができるのに似ている。
これが世界初のRNA(リボ核酸) 分子だ。
のちにDNA(デオキシリボ核酸)へとつながる物質である。
池に再び水が満ちたとき、この原始の遺伝物質は脂肪酸に閉じ込められ、
微小な石鹸の泡のようなものができた。
細胞膜の誕生である。
やがて1週間もすると、浅い水溜まりは無数の小さな泡に覆われて、黄色い膜が張ったようになった。
1つ1つの微小な泡はいずれ細胞となるものであり、
内側には短い糸のような核酸が何本も詰まっている。
これが今日でいう遺伝子だ。
こうした細胞の原形はほとんどが不安定で、すぐに崩壊して材料が再利用される。
しかしなかには長く安定を保って、原始的な代謝の仕組みを発達させるものが現われる。
ついにはRNAが自らの複製をつくり始めた。
生命が誕生した瞬間である。
遺伝物質の詰まった脂肪酸の泡としてひとたび生命が形づくられると、
それらは覇権を賭けて競い合うようになる。
すべてに行き渡るだけの資源などない。願わくば最良の泡が勝利せんことを。
きわめて小さく、壊れやすい生命は、日に日に進化して複雑な形態をとるようになる。
そしてしだいに川や湖へと広がっていった。
そのとき新たな脅威が訪れる。乾季がいつもより長引いたのだ。それまでも、泡の膜に覆われた湖の
水位は乾季になれば大幅に下がっていた。
しかし、雨が戻ってくればかならず元通りに水が満ちた。
ところがこの年、はるか彼方で異様に激しい火山活動が起きた影響で、
毎年同じ季節に降っていた雨が落ちてこない。
雲はただ通り過ぎていき、湖は完全に干上がる。
あとには、乾いて硬くなった黄色の膜が残った。
それが湖の底を厚く埋め尽くしている。
かつて湖は1年を通して水量の変動があり、生命もそれに適応していた。
だが、今やそこは生き延びるための壮絶苦闘の場と化す。
しかも、その闘いには未来がかかっていた。
勝利したものが、やがて登場するすべての生物(古細菌、細菌、真菌、植物、動物)の祖先となるのだから。
大量の細胞の塊は最低限の栄養と水分を求めて争い、どうにか命をつなごうとする。
それでも、死滅への道をたどりつつあった。
増えたいという根源的な欲求に応えるべく、個々の生命は奮闘する。
やがて一風変わった生命が現われた。仮にそれを「マグナ・スペルステス (Magna superstes)」と呼ぶとしよう。ラテン語で「偉大なる生き残り」の意味だ。
生殖か、修復か厳しい環境を生き残るための仕組み
マグナ・スペルステスは、見た目こそ当時の生物と大差ないものの、
ほかより明らかに有利な特徴を1つもっていた。
生き残るための遺伝子メカニズムを発達させていたのである。
この先、数十億年が過ぎていくあいだには、
生命はいくつもの複雑な進化のステップを経ていくことになる。
結果として劇的な変化がもたらされるおかげで、
まったく異なる生物群がいくつも誕生していくほどだ。そうした変化 (遺伝子の変異や挿入や再配列、あるいは遺伝子が生物から生物へと広がることによって生じたもの)の末に生命は左右対称になり、
立体視を獲得し、意識までをも手に入れていく。
それに比べて、この初期の生命に訪れた進化のステップは一見すると単純に思える。
それは1つの回路、遺伝子の回路である。
回路は「遺伝子A」から始まる。
遺伝子Aはいわば監督者であり、環境の厳しいときにスイッチが入って細胞の分裂を停止させる役目をもつ。この「環境の厳しいとき」というのがミソだ。
というのも、当時の地球では環境の厳しいときがほとんどだったからである。
この回路にはもう1つ「遺伝子B」が関わっている。
遺伝子Bからつくられるタンパク質は「抑制」の機能をもっている。
何を抑制するかといえば、環境が好ましいときに遺伝子Aが働かないようにするのだ。
つまり細胞が増殖できるようになる。
いい換えれば、自分の子孫が生き延びる確率の高いときだけに、
細胞が自らの複製をつくれ
るようにするのである。
A・Bどちらの遺伝子も目新しいものではない。
湖にいる生命はすべてこの2つの遺伝子をもっている。
ただ、マグナ・スペルステスが特別だったのは、
遺伝子Bが変異を起こして別の役割も獲得したことだ。
その役割とはDNAの修復である。
細胞のDNAが壊れると、遺伝子Bからつくられるタンパク質は遺伝子Aから離れてDNAの修復を助ける。
「抑制」していたタンパク質がいなくなるので、
遺伝子Aにスイッチが入る。
これによって、DNAの修復が終わるまではいっさいの生殖が行なわれないという重大な結果がもたらされた。
これは理にかなっている。
DNAが壊れているとき、生物が最もしてはいけないことが生殖だから
だ。
たとえば、のちの時代の多細胞生物がDNAの修復中に細胞の活動を停止できないとしたら、
まず間違いなく遺伝物質をなくすことになる。
なぜかといえば、細胞分裂に先立ってDNAの2本鎖が2つに分かれるとき、
一部分しかきれいにほどけず、残りの部分がどちらか一方に一緒に引っ張られて
いってしまうからである。
これが起きると、染色体の一部が失われたり重複したりする。
そうなれば細胞は死滅するか、さもなければ無秩序に増殖して腫瘍になる見込みが大きい。
新しい種類の遺伝子を手に入れて、
増殖を抑制すると同時にDNAを修復できるようになったことが、
ほかにはない強みをマグナ・スペルステスに与えた。
DNAが傷ついているときは、いわば首をすくめてその時期をやり過ごし、やがて復活する。
生き残るにうってつけの仕組みを獲得したのである。
それは幸いだった。
というのも、生命は新たな攻撃にさらされようとしていたからである。
彼方の恒星が爆発して強力な宇宙線が地球に降り注ぎ、
死の湖にすむ微生物すべてのDNAをずたずたに裂い
たのだ。微生物の圧倒的大多数は、何事もなかったかのように分裂を続けた。
自分たちのゲノムが損傷し、
生殖すれば死が待っていることに気づかないまま。
母細胞と娘細胞とのあいだでDNAが均等に分かれず、
どちらの細胞の機能にも支障をきたす。
しまいには生殖など望むべくもなくなる。
細胞は死に絶え、何も残らなかった。
いや、マグナ・スペルステス以外は何も、ということである。
宇宙線が猛威を振るっているとき、この生物は尋常ならざることをした。
タンパク質BがDNAの損傷を治すために遺伝子Aから離れた結果、遺伝子Aのスイッチが入り、
ほぼすべての細胞活動を停止したのである。
限られたエネルギーをDNAの修復に振り向けるためだ。
増えよという原初の指令に逆らったおかげで、マグナ・スペルス
テスは生き延びた
最後の乾季が終わりを告げ、湖に再び水が満ちたとき、
マグナ・スペルステスは目を覚ました。今なら子孫を残すことができる。
だから繰り返し繰り返し増殖した。
やがて新しい環境へと移動し、進化を続け、新たな世代を次々に生み出していった。
この生物こそが私たちのアダムとイブである。
アダムとイブがそうであるように、マグナ・スペルステスが実在したかどうかはわからない。
だが、
過去25年に及ぶ私の研究を踏まえるなら、
今日私たちの周りにいるすべての生物がこの「偉大なる生き残り」から、
または少なくともそれとよく似た原始生物から生まれたと考えてよさそうだ。
生物の遺伝子には、いわば化石記録のようなものが残っている。
それを調べると、地球を共有しているどんな生命も、
この原初のサバイバル回路の基本形を(多少の差異はあるにせよ)今なお抱えもっていることがわかる。
どの植物も、どの真菌も、どの動物も。
もちろん人間も、だ。
なぜこの遺伝子回路は進化の過程で消えなかったのか。
それは、ときに残酷でときに恵み深い世界を
確実に生き延びるうえで、この回路が簡潔で気の利いた解決策を与えてくれるからである。
いわば原初のサバイバルキットだ。様々なストレスが寄ってたかってゲノムを痛めつけているときには損傷の修復に専念し、もっと好ましい時期が訪れたときにだけ生殖を許す。
そうやって、最も必要とされる場所にのみエネルギーを振り向けるわけだ。
この回路はじつに単純にして、じつに堅牢な仕組みである。おかげで、生命が地球上に存在し続けらるようになった。
第1部 私たちは何を知っているのか(過去)
水位は乾季になれば大幅に下がっていた。しかし、雨が戻ってくればかならず元通りに水が満ちた。と
ころがこの年、はるか彼方で異様に激しい火山活動が起きた影響で、毎年同じ季節に降っていた雨が落
ちてこない。雲はただ通り過ぎていき、湖は完全に干上がる。
あとには、乾いて硬くなった黄色の膜が残った。 それが湖の底を厚く埋め尽くしている。かつて湖は
1年を通して水量の変動があり、生命もそれに適応していた。だが、今やそこは生き延びるための壮絶
苦闘の場と化す。しかも、その闘いには未来がかかっていた。勝利したものが、やがて登場するすべ
ての生物(古細菌、細菌、真菌、植物、動物)の祖先となるのだから。
大量の細胞の塊は最低限の栄養と水分を求めて争い、どうにか命をつなごうとする。それでも、死滅
への道をたどりつつあった。増えたいという根源的な欲求に応えるべく、個々の生命は奮闘する。 やが
て一風変わった生命が現われた。仮にそれを「マグナ・スペルステス (Magna superstes)」と呼ぶとしよ
う。ラテン語で「偉大なる生き残り」の意味だ。
生殖か、修復か厳しい環境を生き残るための仕組み
マグナ・スペルステスは、見た目こそ当時の生物と大差ないものの、ほかより明らかに有利な特徴を
1つもっていた。生き残るための遺伝子メカニズムを発達させていたのである。
この先、数十億年が過ぎていくあいだには、生命はいくつもの複雑な進化のステップを経ていくこと
になる。結果として劇的な変化がもたらされるおかげで、まったく異なる生物群がいくつも誕生してい
くほどだ。そうした変化 (遺伝子の変異や挿入や再配列、あるいは遺伝子が生物から生物へと広がるこ
とによって生じたもの)の末に生命は左右対称になり、立体視を獲得し、意識までをも手に入れていく。
それに比べて、この初期の生命に訪れた進化のステップは一見すると単純に思える。それは1つの回
路、遺伝子の回路である。
回路は「遺伝子A」から始まる。遺伝子Aはいわば監督者であり、環境の厳しいときにスイッチが
入って細胞の分裂を停止させる役目をもつ。この「環境の厳しいとき」というのがミソだ。というのも、
当時の地球では環境の厳しいときがほとんどだったからである。この回路にはもう1つ「遺伝子B」
が関わっている。遺伝子Bからつくられるタンパク質は「抑制」の機能をもっている。何を抑制する
かといえば、環境が好ましいときに遺伝子Aが働かないようにするのだ。 つまり細胞が増殖できるよ
うになる。いい換えれば、自分の子孫が生き延びる確率の高いときだけに、細胞が自らの複製をつくれ
るようにするのである。
A・Bどちらの遺伝子も目新しいものではない。湖にいる生命はすべてこの2つの遺伝子をもって
いる。ただ、マグナ・スペルステスが特別だったのは、遺伝子Bが変異を起こして別の役割も獲得し
たことだ。その役割とはDNAの修復である。細胞のDNAが壊れると、遺伝子Bからつくられるタ
ンパク質は遺伝子Aから離れてDNAの修復を助ける。「抑制」していたタンパク質がいなくなるので、
遺伝子Aにスイッチが入る。これによって、DNAの修復が終わるまではいっさいの生殖が行なわれ
ないという重大な結果がもたらされた。
これは理にかなっている。DNAが壊れているとき、生物が最もしてはいけないことが生殖だから
42
第1部 私たちは何を知っているのか(過去)

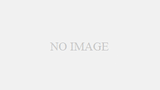
コメント