世界の富裕層が通う「スイスの寄宿学校」
海外の富裕層の多くが、子息をスイスのボーディングスクールに留学させている。
世界中の「特権階級」の子どもたちと寝食を共にして学ぶため、
卒業後に世界中に広がる人脈が大きな財産になるからである。
スイス留学専門家の田山貴子氏に話を聞いた。
ボーディングスクールは日本語にすると「寄宿学校」となり、基本的には全寮制となっています。
日本ではまだ数が少ないですが、欧米を中心に世界各地にあります。
特にスイスのボーディングスクールには海外の富裕層の子息が数多く留学しているということもあり、日本でも以前から富裕層の方々の間でスイス留学はよく知られていました。
スイスのボーディングスクールの留学費用は年間で2〜3千万円かかります。
そのため、もともと限られた人たちしか留学することができませんでしたが、
昨年のさらなる円安の影響を受け、今では「超」が付く富裕層でないと、
子息をスイスに留学させるのは難しくなっています。
それが逆にスイス留学の価値をさらに高めることになり、
以前にも増して富裕層の方々に注目されているところがあります。
富裕層が高額な教育費を投じてでも子息に留学させるスイスのボーディングスクールにはさまざまな魅力がある。
エイグロン・カレッジ校
例えば、スイスアルプスの山岳地域にあるエイグロン・カレッジ校では、
留学生の国籍が65か国と多岐にわたっている。
スイスのボーディングスクールにおける留学生の国籍構成はその時々の国際状況を反映しており、どの国の景気がいいかがよく分かります。
なので、ここ数年は中国とロシアおよび旧ソ連諸国からの留学生が多く、日本人は一時期に比べるとかなり減っています。
勉強量がかなり多い国際バカロレアのカリキュラム
そしてもう一つの大きなポイントが、高校課程で提供されている教育プログラムです。
特に、IB(国際バカロレア=国際的な大学入学資格試験、教育プログラム)を希望する場合、
その学校で学ぶことで希望するIB教科が提供されているか、またIBで高得点を取れそうかどうかです。
学校によっては毎年のように生徒のIBの平均得点が高いところもあり、
高校卒業後は海外のいい大学に進学したいと考えている場合は、
そのような学校を選択する留学生もいます。
IBは、2年間で所定のカリキュラム7教科を履修する必要があり、そのうえで最終試験を受けて、国際的に認められる大学入学資格(国際バカロレア資格)を取得することができます。
IBのカリキュラムは勉強量がかなり多く、2年間、精神的にも鍛えられます。
さらに、スイスのボーディングスクールでは勉強だけでなく時には肉体的に負荷が高い屋外アクティビティにも参加する必要があり、限られた時間のなかで勉強や課題もこなしていかなければなりません。
しかしそれを乗り越えれば、それに見合った学力や教養がつき、
厳しいスケジュールの中で時間をやりくりしていったことは、社会人になってからも生きてきます。
勉強以外では、本格的にスポーツに取り組める学校を選ぶ例もあり、
ある留学生などは、山間部にある学校に入り、スキー競技のチームに入って練習しています。
学校によっては、スポーツの活動に合わせて、
通常なら2年間の課程を3年かけて学べるようにプログラムを組んでくれるところもあります。
ホグワーツもボーディングスクールの一つだった
また、親元を離れて寮生活をすることで自立心が養われ、国際色あふれる同年代の留学生たちと一緒に暮らし、学ぶことで、多言語によるコミュニケーション能力や公共の精神も磨かれていきます。
それだけでなく、礼儀や儀式、規則が厳しい学校が多いので、自制心や協調性、マナーも自然と身についていきます。
世界中の「特権階級」の子息たちと寝食を共にし、学ぶ。
これにより子供時代に築かれた交友関係は、卒業後も切れることがなく、
将来的には世界中に広がる特権階級の人脈が大きな財産になります。
これこそが、富裕層の人たちが自分の子どもをスイスのボーディングスクールに留学させる大きな理由の1つです。
ボーディングスクール発祥の国であるイギリスでは
、15〜16世紀にかけて創設された寄宿学校がその基になっています。
歴代のイギリス王室や貴族の方々もボーディングスクールで学んでおり、
チャールズ国王はスコットランドにあるゴードンストウン、子息のウィリアム皇太子とヘンリー王子の二人はイートン・カレッジという名門ボーディングスクールを卒業しています。
また、世界的ベストセラーで大ヒット映画にもなった『ハリー・ポッター』の舞台となっているホグワーツ魔法魔術学校もボーディングスクールの一つです。
スイスのボーディングスクールで魔法を学ぶことはできませんが、物語に登場する主人公たちのように、多感な思春期の間に多くのことを学び、損得勘定なしの人間関係を築いていくことができるのです。

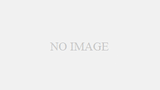
コメント