数式を使わない統計学入門
ダレル・ハフ/著
高木秀玄/訳 講談社
1968.7
数年前の冬、一〇人ばかりの医者が、それぞれ別個に、抗ヒスタミン剤についての調査
結果を発表した。
どの報告も、かなりの割合のカゼが抗ヒスタミン剤を服用した後で直っ
たことを明らかにしていた。
つづいて、ちょっとした騒ぎが、少なくともその広告につい
て持ち上がり、それから薬品ブームがつづいたのである。それは、人々の薬に対する際限
のない期待、そしてまた、統計数字ほどには、昔から知られている事実を信じようとはし
ない奇妙な態度が原因なのであった。
ユーモア作家であって、権威ある医者などではないヘンリー・G・フェルゼンがずっと
前にいっていることだが、カゼなどは、適切な手当をすれば七日のうちにも直るだろう
が、そのままにしておいてもたかだか一週間ぐずつくくらいのものなのである。
読者諸君が読んだり、聞いたりすることについても同様のことがいえる。
平均とか、相関関係とか、トレンドとか、グラフなどは、かならずしも示されている通りのものではな
い。
眼に見える以上の意味があるかもしれないし、見かけより内容がないかもしれない.
統計学という秘密の言葉は、事実がものをいう社会では、人に訴える力が非常に大きい
ので、物ごとを評判にしたり、誇張したり、混乱させたり、また極度に単純化してしまう
のによく利用されている。
それに、統計的な方法や統計用語は、社会や経済の動向、企業の経営状態、世論調査、国勢調査などの膨大なデータの結果を記録するには欠かせない。
しかし、そういった言葉を正しく理解して使う人と、その言葉の意味がわかる
人とがそろっていなければ、結果はナンセンスな言葉の遊びにすぎないのである。
「ひとはけの紅白粉で、人が変わったように美しくなるように、統計によって、多くの重
要な事実が見違えるようになる」
とはいえ、いくら上手にとりつくろった統計数字といえども、
ヒトラーの〝大ボラ”よりはましである。
なるほど、それは人をだましはするが、
そのためにどうにも動きがとれなくなることはないのだから。
この本は統計を使って人をだます方法についての入門書のようなものである。どちらか
はといえば、サギ師のための手引書のようなものである
私はこんな本が当然あってもよいと思う。
というのは、ある泥棒が隠居後に書いた思い出話が、泥棒仲間では、
カギのこじあけ方や足音の忍ばせ方についての卒業講義にも等しいものになっていると聞いた
サギ師たちはこういった手くだを知っているのであるから、正直な人たちもだまされない
ように、彼らの使う手を知っておく必要があると考えるからである。
マルクスの数字はこけおどし
かのカール・マルクスのやったことも、同じような方法で、いかにも正確らしい感じを
だしたというだけのことなのだ。
ルクスは、紡績工場での「剰余価値率」を計算するのに、
素晴らしいほど多くの仮定、
推測、概数を始めに設けている。
「くずは六%と仮定する・・・・・・、原料費は概算で三四二1
ポンドである。一万個の紡錘は、一個の原価が一ポンドと仮定し、・・・・・その磨損は一〇%
としよう。工場建物の賃借料は三〇〇ポンドと推定しておく・・・・・・」といった具合であ
る。
そして、マルクスは書いている。「私はこれらの信頼できるデータをマンチェスター
のある紡績工場主から手にいれた」と。
マルクスは、これらの近似値から次のような計算をしている。

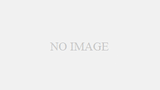
コメント