ウクライナに対して“塩対応”を決め込むトランプ政権。日本でも批判的な言説が多いが、元外交官の亀山氏はそうした見方に否定的だ(写真:UPI/アフロ)© 東洋経済オンライン
2月28日にホワイトハウスで行われたドナルド・トランプ大統領とウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談は激しい口論となり、予定していた鉱物資源の権益をめぐる合意文書への署名が見送られるという、あまりにも衝撃的な形で物別れに終わった。
さらにトランプ政権は3月3日、ウクライナに対する軍事支援の一時停止を発表した。こうした一連の事態を受けて、ウクライナや欧州諸国は大きく動揺している。
そしてわが国でも、トランプ政権の“塩対応”に対して批判的な声が聞かれる。だが、歴史的に見れば、トランプ大統領の対応は必ずしも異常なことではない。
アメリカに流れる2つの外交的伝統
日本人には「アメリカがずっと“世界の警察官”だった」と考えている人が多い。しかし実際には、2つの異なる外交の伝統がある。
1つは、モンロー主義に代表される保守主義だ。これは「旧世界」、すなわち欧州の政治のいざこざには巻き込まれないようにするという孤立主義である。もう1つが、20世紀になって生まれた「リベラルな世界秩序」をリードする外交政策であり、いわゆる「ネオコン」もこの流れである。
トランプ大統領流の「アメリカファースト」とは、実はアメリカの伝統的な保守主義の系譜に連なるものなのだ。
一方の欧州は、ゼレンスキー大統領との会談に関してトランプ大統領を批判し、ウクライナに連帯を示している。これには欧州特有の理由がある。それは欧州の脆弱な安全保障環境だ。
欧州は多民族・多文化・多言語の集合体であり、欧州ほど戦争を繰り返してきた地域はほかにない。2度の世界大戦の結果、荒廃した欧州は、アメリカが強く関与する形で安全保障体制を形成してきた。それが北大西洋条約機構(NATO)である。
しかし、欧州への関与に消極的だったアメリカをNATOに巻き込んだのは、イギリスなどの欧州側であった。ソ連封じ込め政策の立案者として知られるアメリカの外交官、ジョージ・ケナンなどは、西欧勢がアメリカを西欧防衛に引きずり込もうと画策するのは我慢がならないと考えていた。
つまり、ソ連の軍事的脅威に怯える西欧が、ソ連の強大な軍事力に対抗するためにアメリカの力を借りるという構図こそ、半世紀近く続いた「冷戦」構造の本質だったのである。
ちなみに、「冷戦」構造が成立するまで、アメリカとロシア(ソ連)は歴史的に比較的良好な関係を築いていた。イデオロギーにこだわらなければ、双方の勢力圏や利益が衝突することがなかったからである。
プーチンを悪く言わないのは確信犯?
トランプ大統領は今、米欧ロの関係のありかたを根本的に変えようとしている。トランプ大統領がロシアに融和的に見えるのは、ウラジーミル・プーチン大統領に篭絡されているからではない。停戦を実現することで、ロシアの脅威におびえる欧州の不安を緩和し、ゆくゆくは欧州の安全保障から手を引くための布石である。そう考えれば納得がいく。
改めてアメリカを引き込んで「冷戦」的な米ロ対立構造を現出させたい欧州に対して、トランプのアメリカはモンロー主義に回帰しようとしている。「旧世界」のいざこざに巻き込まれることなく、自国の繁栄に注力したいと考えている。
同時に、ロシアと融和することで中ロの結束を無効化することも期待しているだろう。だから、トランプ大統領が停戦を唱えて、プーチン大統領を悪く言わないのは、確信犯なのである。
ちなみに、アメリカがこういう形で手のひら返しをするのは初めてではない。やはり保守主義者であったリチャード・ニクソン大統領が1971年、同盟国・日本の頭越しに中国との関係改善に動き、「ニクソンショック」と呼ばれたことはよく知られている。
このときは、ベトナム戦争を終結させ、アメリカ軍をベトナムから撤退させるとともに、中国と関係改善することでソ連を牽制することが目的だった。ウクライナをめぐるトランプ政権の行動とよく重なるではないか。ただし、今度は中国を牽制するためにロシアと関係改善しようとしている点で対照的である。
わが国では、米ウ首脳会談を受けて、アメリカは「偉大な国」とは程遠いとか、トランプ大統領はプーチン大統領に操られているといった批判も見られる。そうした批判の背景にある心理は「アメリカには日本やウクライナのような弱い同志国を守ってもらいたい」という願望ではないだろうか。
言い換えれば、アメリカは同盟国のために金や軍事力を使うべきだという主張である。これは非常にナイーブな感覚だと言わざるをえない。
ドイツ系のアメリカの政治学者ハンス・モーゲンソーは「弱い同盟国の言いなりになるな」と指南している。トランプ大統領はその指南に忠実であるようだ。
トランプ主義を非難するのは自由だが、安全保障をアメリカに依存する日本も他人事ではない。まずはトランプ大統領の政治姿勢を理解し、対応策を検討することが必要だ。
問題があるのはロシアだけではない
それでも「侵略者ロシア」はけしからんと考えている人々も多いだろう。それはそのとおりだが、重要なのは「ロシアだけが問題なのではない」ということだ。
米中を含め、力を有する大国は皆それぞれに横暴であり、問題なのである。そこで、ロシアとウクライナをめぐる欧米日で繰り返されている以下のような言説を吟味してみたい。
・ プーチンは「独裁者」であり、ロシアでは自由が抑圧されている
・ ロシアは国際法における侵略者である
・ ロシアはさらなる領土の拡大をもくろんでいるため、ウクライナを支援し、ロシアを止めなければ、何か大変なことが起こる
・ ウクライナを守るのは自由民主主義を守るために必要であるため、アメリカはウクライナを支援する義務がある
・ 今停戦すればロシアを利することになり、不公平だ(正義が行われない)
まず、プーチン大統領が独裁者かどうかであるが、プーチン大統領はロシアの法律に基づいて正当に選出されており、2月時点の支持率も88%と極めて高い。国民の73%はロシア国内の物事は正しい方向に進んでいると答えている。
ロシア国民がプーチン政権を恐れて本当のことを言えないのではないかと疑う向きもあるが、それは考えすぎである。この世論調査結果を出している機関自体が、ロシア政府から「外国エージェント」に登録されているくらいである。
次に、ロシアが国際法上の侵略国であるかという点だ。これはまあそうだろうという気がするが、事はそう単純ではない。国家主権は神聖不可侵とされているが、同時に人道や自衛権、自決権といった相反する価値があるからだ。
ロシアの論理構成はこうだ。ロシアは軍事侵攻の直前にドンバス地域のドネツクとルガンスクの独立を承認し、「国家間」の相互援助条約を締結した。これを踏まえて、集団的自衛権を行使し援助義務を果たすため、ウクライナで軍事作戦を展開したとする。
また、ドンバスなど4地域の併合については、住民投票の結果であり、住民の自決権の発露であるとしている。地域が所属する国家から独立する例は、これまでにも確かにある。代表的なものが、コソボのセルビアからの独立である。
ちなみに、コソボ関連では「人道」を理由にNATOも軍事介入したほか、コソボの独立を支持している。まさにドンバス紛争とパラレルな関係にあるわけだ。なお、ロシアはコソボの独立に反対している。
わが国には、安易にウクライナと日本を比べたり、北海道がクリミアのように併合されるのではといった懸念も聞かれる。だが、まったく事情も背景も違うので、同列に扱うことは不正確で無意味な議論を招くだけである。
領土拡大意欲は欧州のプロパガンダ?
3つ目に、ロシアはさらなる領土の拡大をもくろんでいるかどうかだが、その非現実性をロシアはよく理解しているだろう。ポーランドやバルト三国を占領して統治するだけの国力はどこにもないからである。
これも取り越し苦労である。というよりも、冷戦時の経緯を知っていれば、アメリカを欧州の安全保障に関与させておくための欧州のプロパガンダという見方さえできるだろう。
4つ目に、ウクライナを守ることが自由民主主義を守ることかどうかであるが、これはまったくの空論であろう。
そもそもウクライナは国家であり、自由民主主義は政治思想である。同じものではない。単なるレトリックである。
そして重要なのは、ウクライナは自由民主主義のために戦っているのではなく、自国の領土を奪還するために戦っているということである。自国の領土を守るのは国家の義務であるが、それはウクライナ自身の義務であり、他国の義務ではない。また、国家には国民を守る義務があることも忘れてはならない。
今こそ「現実主義的な国際政治」が必要だ
最後に、今停戦すればロシアに有利に決着するので不公平だというものだが、まさにそのとおりと言わざるをえない。そのため、ウクライナは交渉で優位に立つための材料を必死で探し求めている状況である。それでも、事ここに至っては、いかんともしがたいのである。
侵攻前にミンスク合意が履行されていれば、ドンバス地域はウクライナの中の自治州でとどまっただろう。2022年の侵攻直後の停戦合意が実現されていれば、ザポロジエとヘルソンの2州はウクライナにとどまったはずだ。そして今、あまりに多くの犠牲が払われたため、双方ともに引くことができなくなってしまった。
トランプ大統領は「ゼレンスキー大統領が第3次世界大戦を賭け金にカードゲームをしている」と批判したが、これは核心を突いている。なぜなら、ウクライナは一国のみでロシアと対峙することができないからだ。
ウクライナは残念ながらすでに戦場となり破壊されているため、仮にNATO対ロシアの戦争が勃発したからといって、これ以上失うものは多くない。だが、欧州は壊滅するだろう。したがって、ウクライナの主張に寄り添い、歩調を合わせることは、あえて言うが、非常に危険である。
ヒロイズムではなく、現実主義的な国際政治が今ほど必要なタイミングはない。現実主義的な立場をとるものにとって、トランプ大統領の主張は突飛ではない。
ウクライナに武器を支援することは、そのまま戦争を継続することにほかならない。10年支援すれば戦争は10年続き、20年支援すれば20年続くだろう。こうした状況下で、トランプ大統領相手に臆することなく持論を展開したゼレンスキー大統領を勇敢だと称えて拍手を送るのは勝手だが、ある意味で無責任である。
ウクライナ国民はゼレンスキー大統領が持論を述べるのが見たかったのか。それとも、合意が成立するのを見たかったのか。ウクライナ国民の半数以上は、領土奪還を諦めても平和を回復したいという希望を抱くに至っていることを為政者は忘れてはならなかった。
今、欧州は非常に危険な情勢にある。1つでも手を間違えれば、いつでも欧州全土を巻き込むロシアとの戦争に発展する可能性がある。
「勇ましいこと」にこだわるのは危険である。わが国の戦前・戦中の世論や日露戦争終結後の国民の政府批判を想起してもらいたい。
戦争は適切なタイミングでやめなければならない
日露戦争では、賠償金を勝ち取れずにポーツマス条約を締結した小村寿太郎外相は弱腰だと世論に激しくたたかれた。だが、もし交渉が決裂し、戦争が続いていたらどうなっていただろうか。
もっと良い条件が得られたとはとても思えない。日本が負けていたかもしれない。戦争が起きたならば、必ず適切なタイミングでやめなければならない。これがリアリズム政治の英知であるはずだ。
だが今回、トランプ大統領とゼレンスキー大統領との間の信頼関係が決定的に損なわれたことで、トランプ政権の和平構想(プーチン大統領とゼレンスキー大統領の間の和平)は頓挫した。
そもそもプーチン大統領はゼレンスキー大統領を相手に停戦交渉をするつもりがないため、トランプ政権の和平構想はゼレンスキー大統領なしのバージョンになる可能性が高い。
石破茂首相は、今回の会談について「アメリカの側にもウクライナ側にも立たない」と述べた。アメリカの変化を機敏に感じていることがうかがえる対応だ。日本政府には大局を見据えた慎重な舵取りを期待したい。

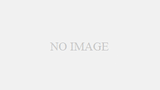
コメント