経営者、従業員、高齢者、若者……「みんな苦しい」のは一体なぜなのか?
私たちを支配する「苦しさ」にはごくシンプルな原因があり、ちゃんと対処する方法がある。経営学の道具を使えば、人生が大きく変えられる。どういうことだろうか。
15万部ベストセラー『世界は経営でできている』で大きな話題を集めた気鋭の経営学者・経営者の岩尾俊兵氏による渾身の最新作『経営教育』(角川新書)では、「みんな苦しい」の謎をあざやかに解き明かす。
(※本記事は岩尾俊兵『経営教育』から抜粋・編集したものです)
人口減少
現代日本は人口減少に直面しています。
このまま人口減少が進むことは避けられない、といった言説もよくききます。人口が減るということは、次の世代の親になれる人自体が減るということです。ということは次の世代の子どもはますます減り、次の次の世代の子どもはさらに……。
しかし、これも根拠のない思い込みかもしれません。
たとえば鬼頭宏『人口から読む日本の歴史』(講談社)に始まる一連の研究・論考では、日本の人口減少局面は実は四度目だという指摘がなされました(図1‐13)。現代日本が歴史上ではじめて人口減少を迎えたわけでもなければ、一度人口減少トレンドが起きると人口が0人になるまでそのトレンドが変わらないわけでもないのです。
日本社会はまず縄文時代後期に人口が3分の1にまで大幅減少しました(図表だとそう見えないのはタテ軸が1000→1万→10万と進む対数表記だからです)。ところが弥生時代には人口は大幅に回復します。そのまま鎌倉時代まで右肩上がりに縄文時代の20倍以上にまで人口が増え続けました。
鎌倉時代後期にはまたしても人口減少します。しかし、室町時代以降に人口は再び上昇して6倍になりました。と、思いきや、江戸時代後期にまた人口は停滞します。すると今度は明治期以降に人口が大幅に増加したというのです。こうして、今の日本は四度目の人口減少を経験しているというわけです。
過去三回の人口減少の波を日本はすべて乗り越えてきていることが分かります。二度ある事は三度ある、ということわざが正しいならば、三度できたことは四度できるという希望も持てるかもしれません。
しかも、過去の日本の人口減少の「乗り越え方」には現代日本の人口減少を考えるヒントがあります。鬼頭名誉教授(上智大学)の研究からは、三度の人口減少を乗り越えた際には常に社会システムの変革があったと示唆されるのです。筆者は、この三度の社会システムの変革の中身について、経営学の視点からの説明もできるのではないかと思っています。
それは、「価値あるものの奪い合いを脱して、価値あるものの創り合いができる方法を見つけた」ということです。それこそが、三度の社会システムの裏側で起こっていたことなのではないか。
つづく「日本の深刻すぎる「人口減少問題」をなんとかする「たった一つの方法」」では、価値の奪い合いからいかにしてい創り合いの世界をつくったのかについて掘り下げる。

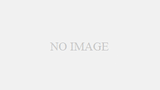
コメント