トランプ大統領は9日、相互関税の一部停止を発表した(写真:ロイター/アフロ)
トランプ米大統領による「関税」が世界を揺るがせています。各国を相手に高い税率の関税を導入したかと思えば、一転して90日間の一時停止を決定しました。トランプ政権の関税政策は目まぐるしい展開を見せていますが、そもそも関税とはどのような役割と仕組みを持っているのでしょうか。知っているようで知らない、関税の「そもそも」をやさしく解説します。
(フロントラインプレス)
「トランプ関税」の経緯を整理
トランプ氏は今年1月に正式就任した後、「米国の産業を守る」として、関税を武器にして矢継ぎ早に政策を決定してきました。わずか3カ月足らずながら変化が激しく、経緯を追いかけるだけでも大変ですが、まずは主な動きを整理しておきましょう。
トランプ支持者も誤解した「関税」の仕組み…国内産業の保護、やりすぎると自由経済体制は崩壊
トランプ政権は、米国の巨額の貿易赤字を減らし、国内産業を保護・育成することに最大の狙いを置いています。そのためには経済のグローバル化を支えた自由貿易体制の変革にも手を付け、関税を引き上げていくというわけです。
同時に、トランプ氏は「ディール(取引)」という語句を盛んに使いながら、米国に協力し続ける国に対しては良い扱いを続けるとの意図も示してきました。そして、矢継ぎ早の関税政策の行方として見えてきたのが「中国の孤立化」です。
相互関税第2弾が発動されると、直後に「相互関税第2弾の90日間停止」を表明。一方では、報復関税を打ち出した中国を標的として、さらなる関税の引き上げを決定したのです。
友好国も含めて全世界を対象に「関税を引き上げる」と宣言する一方、ただちに報復措置を講じなかった国々には「第2弾」を延期。そのプロセスのなかで中国を孤立させているのです。
中国が国際社会での影響力を急速に増す中、トランプ政権は各国に踏み絵を迫り、「中国に付くのか、米国に付くのか」を判断させているのかもしれません。
税率は品目ごとに細かく設定 日本の関税
トランプ政権が武器としている関税とは、どのようなものでしょうか。
日本の財務省は、関税を「一般には輸入品に課せられる税」と定義しています。外国からの物品が商品として自国の領域に入る際(輸入時)、輸入国の政府が輸入業者に課す税金のことを指します。
これとは逆に、自国の領域から海外へ商品が出ていく際(輸出時)、輸出国の政府が課す税金もあります。ただし、現代における主流は輸入関税であり、「関税=輸入品にかかる税金」と理解して差し支えはないでしょう。
関税を課す仕組みはどのような法律で決まっているのか、日本を例にとって見ていきましょう。
日本の関税は「関税定率法」と「関税暫定措置法」という2つの法律によって税率が定められています。「関税定率法」は長期に適用される基本的な税率を定めたもので、2025年4月現在、トータルで7663件の税率が設定されています。
「実行関税率表」を見ると、品目ごとの税率は実に細かく設定されていることに驚くかもしれません。
例えば、「塩及び純塩化ナトリウム(目開きが2.8ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の70%以上のもの及び凝結させたものに限るものとし、水溶液を除く。)」と規定された品目には、1kgあたり0.5円の関税が設定されている、という具合です。
もう1つの「関税暫定措置法」はさまざまな事情により暫定的な税率を定めなければならないケースに対応したもので、現在は412件の税率が設定されています。このほか、途上国の発展を促進させるためといった理由で、国ごとに基本税率より低い関税を設定するケース(特恵)や無税とする例もあります。
関税は国庫への歳入となるため、関税の引き上げは単純に税収増の効果ももたらします。もっとも日本の場合、関税収入の総額(2020年度)はおよそ8300億円。国税収入の1.3%に過ぎませんでした。
自由貿易体制が経済のグローバル化を後押し
税率は商品の輸入価格に対する金額として表示され、納付の義務は輸入業者が負っています。
例えば、パソコンにかかる関税が50%であれば、パソコン1台を10万円で輸入する業者は5万円の関税を自国の国庫に納付しなければなりません。米国では、ごく最近になって「関税は輸出国の政府や業者が米国に収めるものだと思っていた」というトランプ支持者が大勢いたと話題になっていますが、関税を負担するのは輸出国側ではないことに注意が必要です。
関税の上げ下げには、さまざまなプラス・マイナスの効果があります。
関税を上げると、輸入品の価格が上昇するため、その国内での価格競争力が落ちます。したがって、ある国からの輸出攻勢に対抗し、自国の産業を保護・育成したい場合は、その分野・商品の関税引き上げが有力な政策手段となり得ます。
自国の農業を保護するために、農産品に高い関税をかける例がよく知られています。また、関税の対象となった国の産業は、輸出戦略や事業計画の見直しを図る必要に迫られるでしょう。
ただ、戦後の世界経済は米国や欧州が引っ張る形で、自由貿易体制の構築に努めてきました。古くは1947年に成立した国際協定「GATT(General Agreement on Tariffs and Trade、関税および貿易に関する一般協定)」によって、1995年からは世界貿易機関(WTO)によって、関税の壁を低くしたり無くしたりする努力を継続。それが実り、世界経済のグローバル化は急速に進みました。
各国は、過度な貿易摩擦を防止する目的で、ダンピング(不当廉売)に対する関税やセーフガード(緊急関税)などを設けることもあります。それも自由で平等な市場を設けるためという理念に基づいてのことでした。
しかし、トランプ氏はWTOからの脱退を検討しているとされ、実際に現在はWTOへの米国の拠出金を一時停止しています。
関税の歴史
関税の歴史は古く、紀元前には制度が始まっていました。かつては、物品がある地点(関所など)を通過する際に、その地点を管理する者に対して支払わなければならない手数料(通過手数料)のような存在だったとされています。
古代インドでは、紀元前4世紀の政治・経済を帝王学の立場でまとめた書物『実利論』の中に、関税の概要や不払いだった場合の罰則などが登場。メソポタミアと地中海を結ぶ交易路に存在した中東の都市国家・パルミラでは、紀元前135年に「関税法」が公布され、すべての物品や奴隷に関税が課せられました。関税はその後、中世ヨーロッパでも関税は広く採用されていきます。
近代国家が誕生し「国境」が確立すると、関税は国内の物品移動に課すのではなく、主に国境をまたいで行き来する物品を対象とする「国境関税」としての機能を持つようになりました。そして、国際社会に大きな影響を与える存在となります。その端的なケースが第2次世界大戦にもつながった1930年代の出来事でしょう。
1929年、世界の主要な国々は世界恐慌に見舞われました。それを脱するために、植民地を持つ国はそれぞれの決済通貨を軸として経済圏(ブロック)を形成。ブロック内では関税を軽減する一方、ブロック外からの輸入には高い関税をかけたり貿易を制限したりし、自国産業を保護する体制をつくりあげました。いわゆる「ブロック経済」です。
この時期の米国は1930年に「スムート・ホーリー関税法」(1930年関税法)を制定し、3300品目のうち890品目の関税を引き上げました。これにより、米国の輸入関税は平均40%という高率になりました。
オランダやフランス、英国などは直ちに報復関税を設定しましたが、米国への輸出を閉ざされた欧州の経済危機は深刻さを増し、やがてドイツの銀行制度が崩壊します。各国間の経済戦争は悪化し、やがて経済難を背景としたナチス・ドイツの台頭もあって世界は第2次世界大戦に突入したのです。
トランプ政権の関税政策がどう展開するか、まだ明確には見通せません。しかし、仮に大きな路線修正がなければ、世界が再び保護貿易に覆われていく懸念はなくならないでしょう。
フロントラインプレス
「誰も知らない世界を 誰もが知る世界に」を掲げる取材記者グループ(代表=高田昌幸・東京都市大学メディア情報学部教授)。2019年に合同会社を設立し、正式に発足。調査報道や手触り感のあるルポを軸に、新しいかたちでニュースを世に送り出す。取材記者や写真家、研究者ら約30人が参加。調査報道については主に「スローニュース」で、ルポや深掘り記事は主に「Yahoo!ニュース オリジナル特集」で発表。その他、東洋経済オンラインなど国内主要メディアでも記事を発表している。


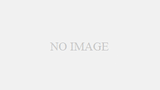
コメント