ご承知のように、日本は、第2次世界大戦で、敗戦を味わいました。
現代に生きる私たちは、当時の日本と米国の経済力格差をよく知っています。
それで、
「なぜ、経済力で圧倒的に劣る日本が、なぜ戦争に踏み切ったのか」
と不思議に思います。
理解に苦しむところです。
とはいえ、戦時に関わるいろいろな話を見聞きすると、
不思議なことがあります。
どういうことかというと、
開戦前、あるいは戦争中でも、
「日本は、米国に敗ける」と語っていた人(もちろん “密かに”ですが)が
意外と多いのです。
東京に住んでいる人だけではありません。
地方に住んでいる人でも、そうした冷静な見方をしていた人がけっこういたようなのです。
「そういう(敗戦)分析をしていた人は、
一体 どうして そんなマクロ情報を知りえたのだろうか?」と、不思議に思っていました。
多くの日本人が「開戦すれば 敗ける」ことを知っていた!
そうした疑問に真っ正面から答えてくれる書物に巡り合いました。
『経済学者たちの日米開戦 秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く』
(牧野邦昭著 新潮社 2018.5)です。
この本を読むと、当時、本に親しんでいた人たちは、だれでも、
「戦争をした場合、日本の国力からして、戦争継続できるのは1年程度。
それ以上継続した場合は、敗ける」という情報を得ていたようです。
そうした分析をしていたのが、本のタイトルにある[秋丸機関]です。
[秋丸機関]というのは、1939年9月、(日本の)陸軍省経理局内に設立された研究組織です。
正式名称は「陸軍省戦争経済研究班」。
対外的名称は「陸軍省主計課別班」。
(満洲国の経済建設に関わった)秋丸次朗主計中佐が率いたチームであることから、
「秋丸機関」と呼ばれています。
何のための研究組織かというと、
「仮想敵国および同盟国の経済戦力を詳細に分析・研究すること」。
総勢200人に及ぶという組織で、
集められたブレーンは、当時のトップレベルの頭脳。
英米班(主査・有沢広巳)、独伊班(主査・武村忠雄)、
日本班(主査・中山伊知郎)、ソ連班(主査・宮川実)、
南方班(主査・名和田政一)、国際政治班(主査・蠟山政道)
という顔ぶれを見ても、そのレベルの高さをうかがい知ることができます。
そこでの分析結果は――というと、
「英米の本格的な戦争準備には一年余りかかる。
日本は開戦後2年は貯備戦力と総動員によって抗戦可能」など、
多岐に渡っています。
「合理性」よりも「ムード」に走った
ただ、中核となる部分については、総合雑誌などにも投稿され、
識者間での議論の対象になっていたということなのです。
つまり、ちょっとしたインテリならば、
「日本が開戦したならば、敗ける」
「もし、開戦しても、1年以内に終結するような交渉をしなければならない」
という情報は 共有していたということになります。
では、そうした合理的な情勢分析をしていながら、
なぜ、戦争に突き進んで行ってしまったか――というと、
多くの国民は、合理的情報を得る努力を怠り、
観念論や精神論といったムードに走って行ったからだといえます。
これは、今の日本にも 十分当てはまります。
その気になれば、情報は、いくらでも集めることができます。
でも、多くの人は そうした努力を怠っています。
手軽な情報、心地よい情報、刺激的な情報、楽しめる情報といったものだけに頼っていて、
自分たちの得ている情報が かなり偏っていることに気づかず、
結果として、偏った方向になびいていることを自覚できない状況にあるといえます。
「自分が得ている情報は、間違っていないか」を常に、
疑問視する必要があります。
これは、知の達人たちが 口をそろえて語っていることです。
心に留めておいた方がいいようです。

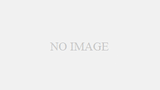
コメント